2011年08月01日
リハーサル山形村朗読講座第9回

次回の本番に向けて、会場である神社でリハーサル。
趣のある、神社風景。あいにくの雨の中だったが、受講生さん達の士気は高く。

声の響き方、視覚的演出、読みのスピード、視線の配分等、演目ごとアドバイス。
その後時間外ながら、社協担当者さんがリハーサル風景をビデオ撮りしてくださり
映像を見ていただく時間をもってくださった。
本番のお天気はよさそう。
2つのグループが、別々の日に本番を迎えます。
集まる子どもの数はおのおの50人は超えるそうな。
がんばれぇ~♪
2011年07月14日
声のベクトル 山形村朗読講座第7回
この講座も残すところあと1回。
その後修了朗読会となる。
今回は、朗読会に向けて、人に声を「意識」して届ける、声のベクトルのワーク。

背中を向けた仲間に誰かに意識をロックオン。
その人に向けて声をかける。
声をかけられたのが自分だと思った人だけ手を挙げる。
どんぴしゃ、ピンポイントでその人だけが手が上がるパターン、
思った方向と真逆に位置する人が手を上げるパターン、
声が拡散してみんなが手を上げるシーンも。
声のベクトルの方向性と届き方の例をあげ、考察。
意識する、ことが大切というところにもっていく。
後半はグループごと作品朗読検討。
ある程度読みこんであるグループは、微妙な間の取り方、ユニゾンのタイミングなどをアドバイス。
まだ分担決めで話し合いが続いているグループもあり、別日に練習時間をとるところも。


次回はゲネプロ。本番の会場である神社に集合して位置決め、光の加減などを考慮し、
本番に備えた練習をする。
その後修了朗読会となる。
今回は、朗読会に向けて、人に声を「意識」して届ける、声のベクトルのワーク。

背中を向けた仲間に誰かに意識をロックオン。
その人に向けて声をかける。
声をかけられたのが自分だと思った人だけ手を挙げる。
どんぴしゃ、ピンポイントでその人だけが手が上がるパターン、
思った方向と真逆に位置する人が手を上げるパターン、
声が拡散してみんなが手を上げるシーンも。
声のベクトルの方向性と届き方の例をあげ、考察。
意識する、ことが大切というところにもっていく。
後半はグループごと作品朗読検討。
ある程度読みこんであるグループは、微妙な間の取り方、ユニゾンのタイミングなどをアドバイス。
まだ分担決めで話し合いが続いているグループもあり、別日に練習時間をとるところも。


次回はゲネプロ。本番の会場である神社に集合して位置決め、光の加減などを考慮し、
本番に備えた練習をする。
2011年07月02日
群読体験 山形村朗読講座第6回
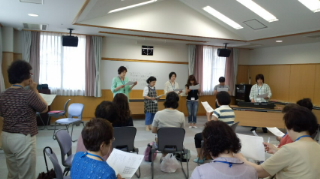
今回葉群読体験。グループに分かれ読み方検討の後、聴き合い会。
群読の手法のあれこれを説明後「いろんな工夫をしてみよう」、と投げかけ。
すると、鳴り物を使ってみようという案が出て、社協職員さんにお願いして倉庫から
いろんなアイテムが。w


結局、鉄琴、キーボード、太鼓、ハンドベル、大正琴、いろんなものを試してみながら
おはなし効果を作り上げていく楽しい時間に。
後半は聴き合い後の考察と本番に向けての出し物グループ会議。


各グループとも、講座時間を過ぎても話し合いは白熱。
今回の講座目的であるチームワーク構築と自己発動による創意工夫はすっかり果たされている。
すごいねぇ。。
次回は、お話会の進行演出と各出し物の朗読検討。
本番まで、あと2回。がんば。
2011年06月24日
なんちゃって腹話術 山形村朗読講座第5回
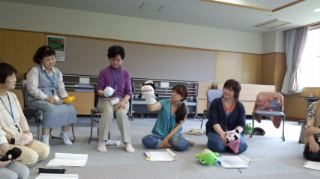
おはなし会準備講座としての特徴。
演目講習のほか、プログラムの組み立て方、場つなぎのアイテムやMC、演出、チームワークなども
講座の中で体感、会得していくこと。
今回は、おはなし会導入部や演目の合間の気分転換アイテムとして
パペットにおはなしをさせる練習。
まずは、自分の担当になったパペットと向き合い、友達になる時間。
つぎに、お名前をつけてパペットにキャラづけをして自己紹介をさせる。
腹話術の手法をとるが、マ行、パ行の発音は修得に技術を要するので、
初歩として歯閉じ腹話術を。唇はうごかしてよいこととし、発音をしてみる。
唇は動かしていいのだが、歯を閉じ発音するだけで通常の数倍、舌の動きを意識することを体感してもらう。
手にはめたパペットと自分の声の連動。さらっとうまくできる人、どちらかかがとまってしまう人いろいろ。
この「連動」させるスキルは、重要で他の部位、場面でも多く応用される。
次にグループ分け。

本番に向けて各グループでおおまかなプログラムをはなしあってもらう。
グループ内で討論検討することで、お互いのおはなし会に対するイメージや希望を共有、統一していく作業。
最後に、群読用のテキストを渡し、各グループで練習。
声パススキルを身につけてもらう試み。
次回は、この群読の完成と他の演目検討。30日の予定。
2011年06月09日
山形村朗読第4講座 紙芝居
前回まで駆け足ながら音声表現と声の要素、発声呼吸をひととおり学習したので
今回から具体的にいろいろな作品を読みながら、それぞれの読み方の体験を。
今回は、紙芝居。
基本的な紙芝居の知識とスキルと実演のあと、
間・声・抜きの基本スキル練習になる5作品を紹介。
作品ごとに班わけをして、仲間同士で作品検討をしてもらい、最後に実演。
班わけは、同じ年齢層で固まらないよう、こちらで組み合わせを指定。
キャラごとに担当、あるいは場面転換で交代、またかけあい、など
それぞれの班で工夫してひとつの作品を演じてくれました。
「みんなで考えてみる」「やってみる」というところがミソ。
チームワークやそれぞれの気性の把握につながるワーク。
笑い声もたくさんでて、ちょっと時間が過ぎてしまったけれど、全員が読むことができました。
年輩受講者の方々は口々に
「若い人たちとこうして同じ土俵で学べる機会はほんと、おもしろくて、もらってるわぁ」と。
世代間交流にもなっている?
よかった。(^-^)
次回は、23日。
プログラム間の演出アイテム「なんちゃって腹話術」と読み聞かせの基本。
2011年05月27日
山形村朗読第3講座 音声表現技術と呼吸
 松本平タウン情報5/26
松本平タウン情報5/26初回の講座日に取材にきてくださっていたタウン情報の記事が載りました。
この講座の紹介をしてくれています。
3回目の講座は、前回の課題だった呼吸のワークと、音声表現技術を。
じゅうたん敷きの会場でしたので、床に座ったり、うつぶせたり、仰向けに寝たり、歩き回ったり、壁を押したり、
と、体を使いながら、呼吸と共鳴の違いを体感しながら、腹式呼吸、中央呼吸を学んでいただきました。
後半は、音声表現。
6つの音声表現をそれぞれ、短文を使って学び、
最後に短い民話文をテキストに、一巡して読み聞かせ体験をしていただきました。
お一人終わるごとに、課題をひとつずつ付け加え、ひとつのおはなしを、どう解釈し、伝えていくかを検討。
初回講座からここまでが、総論のようなもの。
次回から、各論。
紙芝居、絵本読み聞かせ、朗読、語り、などそれぞれの物語の渡し方を学び、
その後、お話会プログラムの構成配慮について、講座は進みます。
次回講座は、6月9日です。
タグ :朗読講座








