2015年07月10日
朗読奉仕員養成⑦音声技術で新聞・広報を読む

さあ、どんどんいくよーということで。短文で音声表現技術の演習をしたあと、
実際の新聞記事、広報の記事を教材に読み方検討を作っていく。
記事は、ピッチ上げ。ピッチ下げ、間、チェンジオブペース、並列読み、プロミネンス、など技術駆使できそうなものをチョイス。
複数の見出しの処理、文字表現のフォント、太字、斜字の違いからくる記事作成者の意図の読み取り、
朗読者註の入れ方についても、言葉変換をしていいもの、しちゃいけないもの、根拠、など後列の既会員、実践組にも問いかけながら
進めて行く。
緊張感が伝わってくるが、既会員でアシスタント当番でないメンバーは学ぶつもりで出席してきているので
ぽんぽんと回答が来て気持ちがよい。
いきなり暑くなったこの日、みな、よみ実践で声を出しまくった講座であったので、水分補給と喉休めタイムを複数回とって進めた。
修了録音の最終日を除いて、後2回。
ラストスパートに入っていく。
2015年07月03日
朗読奉仕員養成講座⑥ ピッチ練習
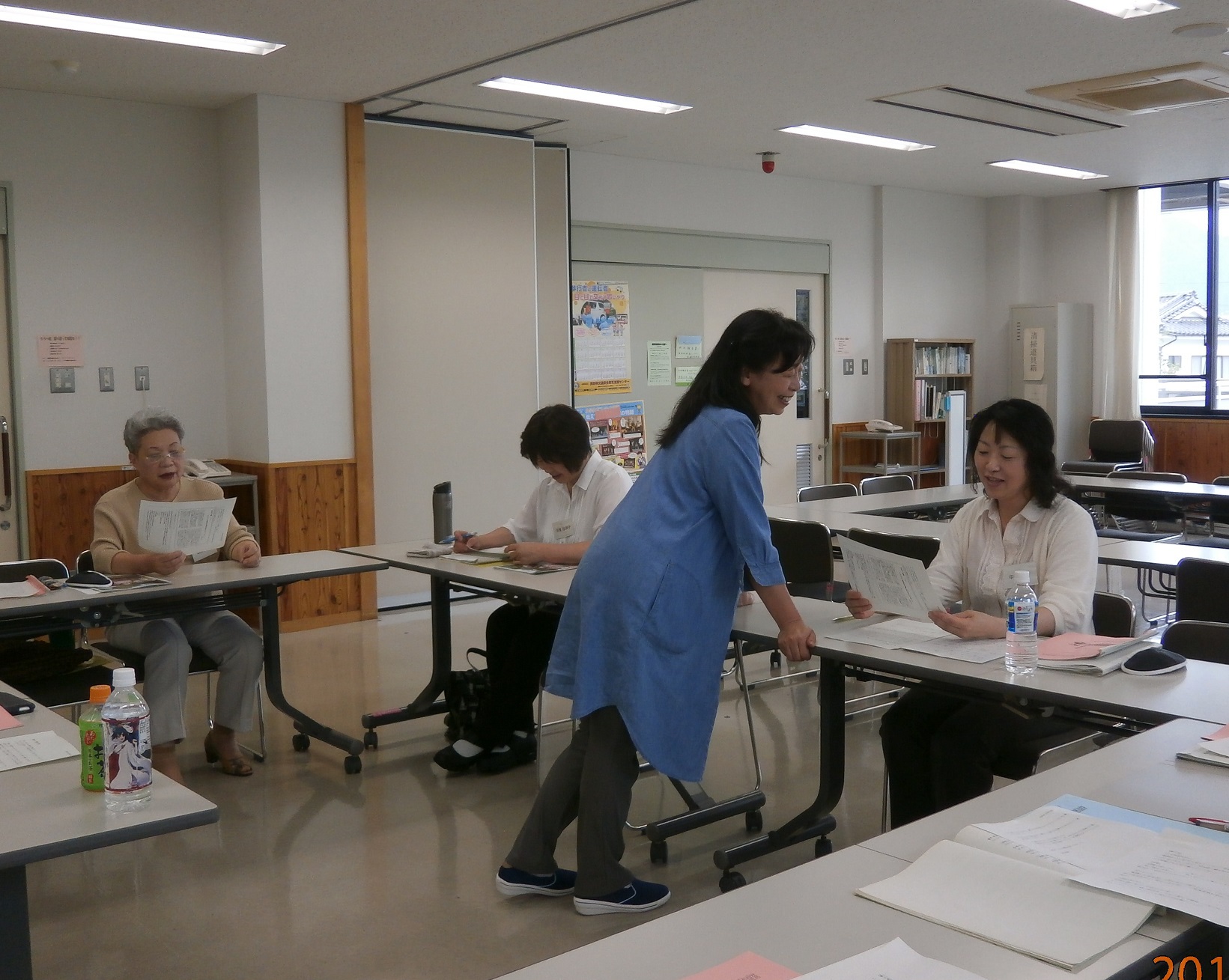
今回から実技。
音声表現の、ピッチ練習。( )内、補足などを読むときにその部分のみをピッチ(声の高低)を変えることで本文との区別を耳に届ける。
普段のピッチ下げは一音くらいだが、慣れてこないと出来ているつもりで全く下がっていないことが多い技術。
そこで、地声の中で一番高い音(このときファルセットにしない)と、低い音を2拍ずつ、上げ下げして練習することで大きく感覚をつかんでいく。
何度か練習したあと、短文で実践。
ほかに、間をとる、スピードを変える、などの工夫で、用意したそれぞれの短文に一番即した音声表現を考えて行く。
ポイントはどこか、を文章の意味を捉えながら探しあう。
喉をフルに使ったので、休憩を少し多めに取り、また短文。
ここまできて、不安が楽しさに変わってきたと最高齢の受講生さんの言葉が嬉しい。
2015年06月29日
朗読奉仕員養成⑤ 適性を知る
前半講座の最終、折り返し回。
後半講座の各論に入る前に、それぞれの適性を探るワークを。

自分の口調スタイルの適性範囲を知るワーク ~ストレッサーをもたない活動のために~
前回文体と口調スタイルの関係を体感していただいたが、その振り幅には個人差がある。
自分にある振り幅の中での移動は訓練できるが、その範囲を超えて、読みの矯正をすることを避けたい。
経験が進めば、その振り幅を広げていくことも楽しみになるが、最初からそれを自分に課すことはストレッサーを抱えることとなり
技術向上の妨げとなっていく。
そこで、まず、読み技術は無視して、自分が読みたいように読んでみる。
続いて、口調スタイルを少しずつ移動し、「あ、違和感:」となる境目を見つけていただく試み。
自然体での読みと、スタイルを意識した読み、その許容範囲は、面白いほど、分かれた。
自分が思っていた自分の範囲と客観的に判断された範囲の違いに驚く人も。
まずは、自分の適正範囲の中で朗読検討を作っていくことを目標としてほしいとお話し、前半部終了。
後半は、写真の非言語情報の伝え方。
宿題にした作文を読んでいただき、お互いに考察。
聴きあう事での気づきを持ってもらう。
次回から、これまで体感してきたことをもとに、各項目ごとの実技指導に入っていく。
最後に前半5回終了時の感想を一言ずつ話してもらっておひらき。

後半講座の各論に入る前に、それぞれの適性を探るワークを。

自分の口調スタイルの適性範囲を知るワーク ~ストレッサーをもたない活動のために~
前回文体と口調スタイルの関係を体感していただいたが、その振り幅には個人差がある。
自分にある振り幅の中での移動は訓練できるが、その範囲を超えて、読みの矯正をすることを避けたい。
経験が進めば、その振り幅を広げていくことも楽しみになるが、最初からそれを自分に課すことはストレッサーを抱えることとなり
技術向上の妨げとなっていく。
そこで、まず、読み技術は無視して、自分が読みたいように読んでみる。
続いて、口調スタイルを少しずつ移動し、「あ、違和感:」となる境目を見つけていただく試み。
自然体での読みと、スタイルを意識した読み、その許容範囲は、面白いほど、分かれた。
自分が思っていた自分の範囲と客観的に判断された範囲の違いに驚く人も。
まずは、自分の適正範囲の中で朗読検討を作っていくことを目標としてほしいとお話し、前半部終了。
後半は、写真の非言語情報の伝え方。
宿題にした作文を読んでいただき、お互いに考察。
聴きあう事での気づきを持ってもらう。
次回から、これまで体感してきたことをもとに、各項目ごとの実技指導に入っていく。
最後に前半5回終了時の感想を一言ずつ話してもらっておひらき。

2015年06月19日
朗読奉仕員養成第4回 文体と口調スタイル

前半はタオルパスワークで、息をそろえると声の音質も揃っていく体感。
その感覚をもって声パス朗読に移行。
その後、あらゆる文章の「文体」と口調の関係性の講義。
実習は、枕草子の口語訳、原文、現代語訳の読み比べで。
後半は、アナウンス原稿をもとに文体から口調を整えていくワーク。
アナウンス気分を出すため、エコーをかけたマイク通しで読み。

残りの時間で広報しおじりの表紙絵の説明作文を宿題にするにあたり、留意点を意見を出し合って考えてもらう。
これはこうやる、のレクチャーを先にせず、すべてを体感から疑問点を持つことからの学びに。
さて。どんな説明文が出来上がってきますか。楽しみです。
2015年06月12日
朗読奉仕員養成第3回 配慮と体験考察

第1回目に録音した自己紹介と2回目に録音した自己紹介文の朗読を聴き比べ、「話すように読む」技術への気づき考察。
自分の声に対する違和感からの脱却と客観視が、最初の壁となるこの活動。
各々で異なる自身の発声、読みに対する課題を把握していただき、作文する時のポイントをお伝えし、完成稿にすることを宿題とする。
その後音声技術のさわりと、声の5つの要素ワーク。
後半は、アイマスクを使って対面朗読のロールプレイング。
目の見えない方に文字あるいは非言語情報をお伝えするには、どう配慮すべきか、体感と考察。
体感から、後期、初級編(技術習得)に移る前に、着目すべき課題を持っていただく。


触感からお伝えする、目次から選択肢をお渡しする、色や目から入る色情報の声変換の試みなど、未経験ながら、創意工夫が見え頼もしい。
今年は驚いたことに、自主学習をしてくる受講生ばかりなので、読み合わせや声リレーがハイレベルで進む。
「かつ舌ではすでに抜かれている感だわ;」とは、見学に来て下さった大御所。
いいねぇ。うれしい。
次回から広報誌を教材に、実践に入っていく。
2015年06月06日
朗読奉仕員養成講座第2回 呼吸と発声アイマスク
前半はアイマスク体験から、視覚以外の感覚でものを感じるという事の体感。
絨毯敷きの部屋で、呼吸と発声のワーク。
観察レッスン、S音、Z音、共鳴、ロングト―ンまで。
つぎに 頭に映像を想像しその解説をするように話すワーク(お気持ちカード)
会議室に移動し、宿題の自己紹介の作文を録音。
その後、声パス、かつ舌練習。これらの基礎を講座内でみっちりやるのは今回まで。次回からは実践読みに入っていくので
以後の基礎練習は自己練習。例年ここから、自主練組と、講座だけの人の差は大きくなっていく。
今年は、どうだろう。素質もあり、やる気も持ってくれている顔ぶれ。楽しみ。
最後に、同行する際の注意事項の読み合わせ。
次回は、声の5つの要素と、音声表現技術に進もう。








