2017年04月14日
朗読ボランティア(奉仕員)養成講座受講生募集2017
視覚に障害のある方々に向けた朗読奉仕員の養成講座を開催します。(全10回)
日程: 5月26日から7月28日までの毎週金曜日 午前10時から正午まで。
場所: 塩尻市保健福祉センター2F 地域福祉推進センター内ボランティア支援室
費用: 1000円 (保険料、資料実費) (講座費用は社会福祉協議会が負担します)
講師: 朗読士® 池内のりえ
内容: 読みの基本・非言語情報の音声化・視覚障害者情報保障・周辺法規等
申込: 塩尻市地域福祉推進センター 電話0263-52-2790
定員:15名 申込順



日程: 5月26日から7月28日までの毎週金曜日 午前10時から正午まで。
場所: 塩尻市保健福祉センター2F 地域福祉推進センター内ボランティア支援室
費用: 1000円 (保険料、資料実費) (講座費用は社会福祉協議会が負担します)
講師: 朗読士® 池内のりえ
内容: 読みの基本・非言語情報の音声化・視覚障害者情報保障・周辺法規等
申込: 塩尻市地域福祉推進センター 電話0263-52-2790
定員:15名 申込順


2016年07月23日
朗読奉仕員養成講座⑨レストランメニューで

前半はロールプレイング。 伝えるワーク。やるなら楽しく。
見えない人に説明、の演習は、ロイヤルホストの夏メニューで。
2人組で一人はアイマスク。制限時間内にメニューを説明して二人分の注文を決める。
ウェイトレスとなって注文を取りに行く私に、主体者が望むような注文ができるかな?。
ちょうどおなかがすく時間、ロールプレイングなのに、各チーム真剣なメニュー選びが展開しました(笑)



後半は次回の修了録音に向けて、課題文のレッスン。
少人数でグループになり、アシスタントで入ってくださった会員の方々にアドバイスに入っていただきました。
次回、いよいよ、最終回となります。
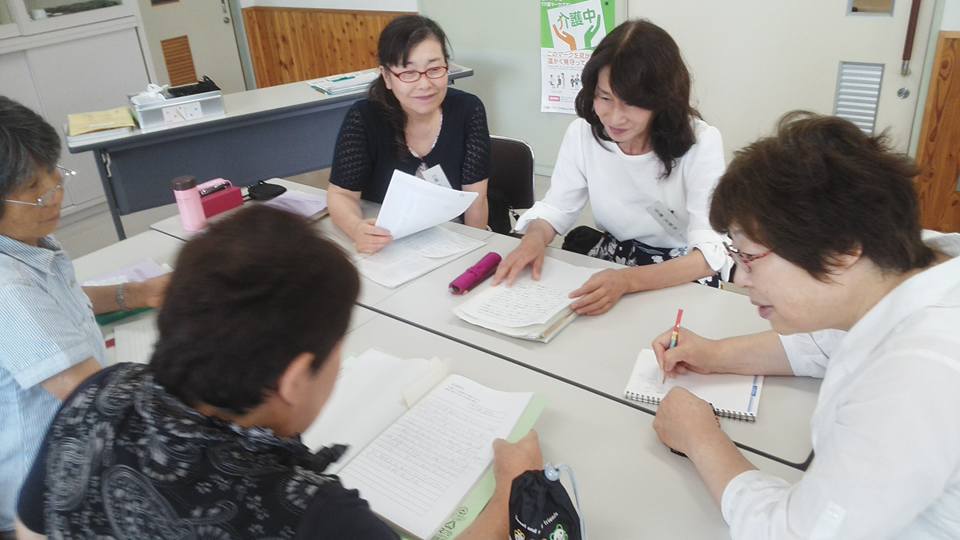


2016年07月19日
朗読奉仕員養成講座⑧「間」のレッスン
「間」あるいは「沈黙」は、朗読表現の中でも最重要技術と言われます。
文章のきる場所によって、情景や感情の伝わり方、また、ときに、意味合いまで大きく変わる「間」
短文で「間」の取り方の例をいくつか演習した後
芥川龍之介の「トロッコ」の冒頭部を教材に、「間」を考えるレッスンを。
検討時間を設け、その後、一人ずつ、自分の検討で朗読。
読みの課題をお渡ししつつ、皆で聞きあう時間をもちました。

2016年07月03日
朗読奉仕員養成講座⑥文字で読まずに意味を読む

テキストはいつも既製の教科書は使わず、手作りをしている。
この全10回のコースでは前半後半を入門、初級と編を分けてお渡ししている。
講座を修了しても、そこからまだ学びは続くんだよ、の思いを込めて「初級」までとしている。
以後は、活動の中で随時、会員相互のフォローアップ講座が開かれているので、そちらにおまかせしている。
予算や期間延長がかなうならば、ほんとうは1年コースで入門、初級、中級、実践、まで編を重ねていきたいところだが。
さて、6回目。初級編のテキストをお配りし、さっそく音声表現のおさらいをたっぷり。
漠然と、文字を音声化することなく、意味のまとまりをつかむことが最重要。
文字で読まずに意味を読むことが、朗読、話すように読めるのは、意味を読むからだよ~の体感ワーク。
後半は非言語情報を作文化する指針をお伝え。
宿題は、広報の表紙写真の音声化。
だんだんお仲間同士も打ち解け、良い感じ。
暑いですが、ご体調にお気をつけて、最後までぜひ。
2016年06月27日
朗読奉仕員養成講座⑤適性を知る

講座第一回目の自己紹介音声と、宿題にして書いてもらった話した通りの自己紹介文の朗読を
個人別に並べてパソコンに取り込んだものを持参。
聴き比べてもらい、「話すように読む」コツを一人ずつ、その特性に合わせてレクチャー。
はなすときと、読むとき、声質が変化してしまう人、二つの音声がまったく同じように聴こえる人、
音量が大幅に変わる人、さまざま故、アドバイスは個々。
以後修了録音までに課題文として自己紹介文の修正、朗読検討を課す。
その後、夏目漱石作品、冒頭部の読み分けで、表現の幅、自己の現時点での許容範囲を探るワーク。
塩尻の朗読ボラの活動は、音訳、対面朗読、影アナ、読み聞かせ、司会等多岐にわたるため
初期研修をどのチームからするのがいいかここで適性を見極めていく。
はじめは、なるべく、自分にストレスがかからない部門が望ましい。
それは「1年の壁」をこえられず挫折いないための大切な見極めだ。
これは、自分は読み聞かせや朗読など、たっぷり情緒型と思っていた人が、
やってみたら音訳読みのほうがノンストレスと気がついちゃったりする場合もあり
カラーコーディネートのような面白さがある。
今回の宿題は、次回からの非言語情報の音声化の最初、写真付き新聞記事をどうよんだら伝わるかの工夫を各自で。
2016年06月20日
朗読奉仕員養成講座④読み方基本5つの要素文体と口調
今期は、途中から受講生の数が2人ほど増えた。
いまのところ、脱落者なし。すばらしい。

いつもの声の準備体操。
丹田呼吸、ハミング一曲、清音~ロングトーン、かつ舌で、30分。
その後、読み方の基本、ポイントを例文を使って解説。
細かな音声表現技術は後半の初級編でやるので、さわりを。
その後、声の表情を声色ではなく、地声の範囲内でつけるための5つの要素を例文で体感。
練習文は、「情報を伝える」ことに特化しているホール影アナ原稿を使って。
主語述語の関係をはっきりつかんで、意味のまとまりをつくる読み方を考える。
各自朗読検討をしてみて、一人ずつマイクを使ってアナウンス読み。

受講生は、ただ、マイクの前に座り、原稿を読むだけ、なんだけど、とっても「あがる」体験を、ここでする。
そして「あがる」と、自分の声はどう変わるかを感じとってもらう事も狙いのひとつ。
次回は文体による口調の変化を感じつつ、それぞれ自身の適性の範囲を探っていく。
いまのところ、脱落者なし。すばらしい。

いつもの声の準備体操。
丹田呼吸、ハミング一曲、清音~ロングトーン、かつ舌で、30分。
その後、読み方の基本、ポイントを例文を使って解説。
細かな音声表現技術は後半の初級編でやるので、さわりを。
その後、声の表情を声色ではなく、地声の範囲内でつけるための5つの要素を例文で体感。
練習文は、「情報を伝える」ことに特化しているホール影アナ原稿を使って。
主語述語の関係をはっきりつかんで、意味のまとまりをつくる読み方を考える。
各自朗読検討をしてみて、一人ずつマイクを使ってアナウンス読み。

受講生は、ただ、マイクの前に座り、原稿を読むだけ、なんだけど、とっても「あがる」体験を、ここでする。
そして「あがる」と、自分の声はどう変わるかを感じとってもらう事も狙いのひとつ。
次回は文体による口調の変化を感じつつ、それぞれ自身の適性の範囲を探っていく。








